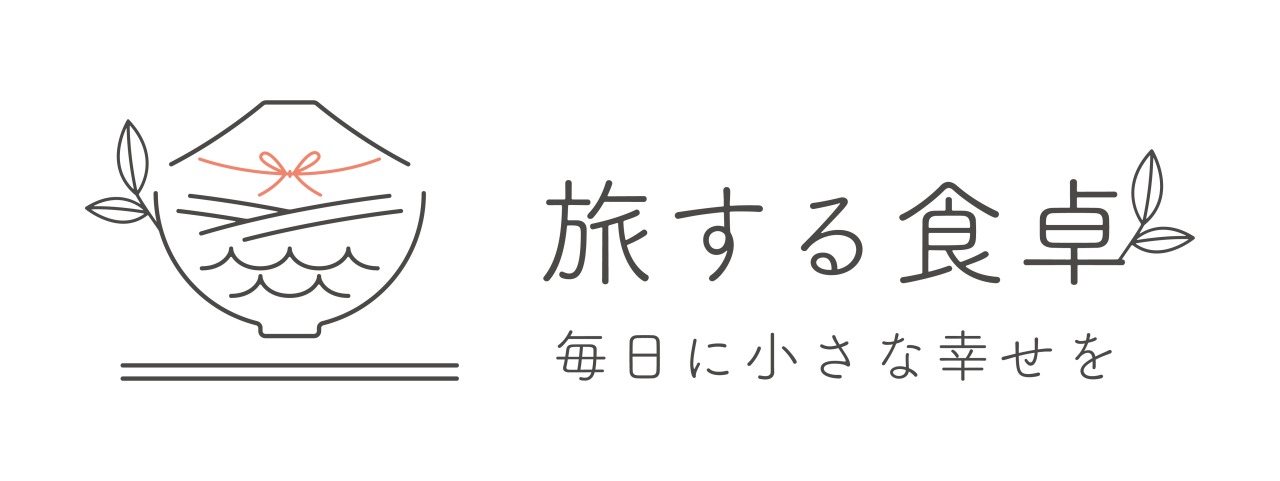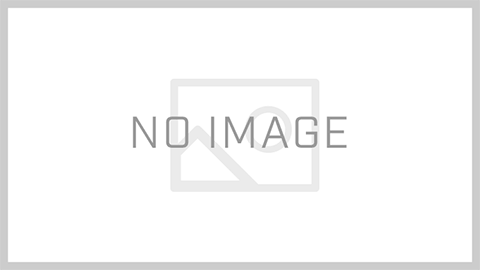おうちで旅気分
「ひたし豆」は東北・信越地方の郷土料理!おいしく食べられるレシピをご紹介
2024年4月1日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
シンプルが一番【ヤスダヨーグルト】は食べる派?飲む派?
2020年10月3日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

見学・体験レポート
【新潟伊勢丹】で見つけた新潟ならではの食のおみやげ3選
2018年6月7日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
人の温かみと優しさを感じた「にいがた人形横町」
2018年1月4日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
新潟の上古町商店街、通称「カミフル」で見つけたステキなものたち
2017年12月26日 旅する食卓編集部 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分
まるで雪のよう!浮き糀味噌で有名な越後味噌「雪の花中辛味噌」
2017年12月5日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分
「しょうゆ赤飯」って何?新潟県長岡のご当地赤飯を作ってみた
2017年12月4日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

見学・体験レポート
新潟名物「笹だんご」作りの体験もできる!「田中屋本店」のみなと工房
2017年11月29日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip