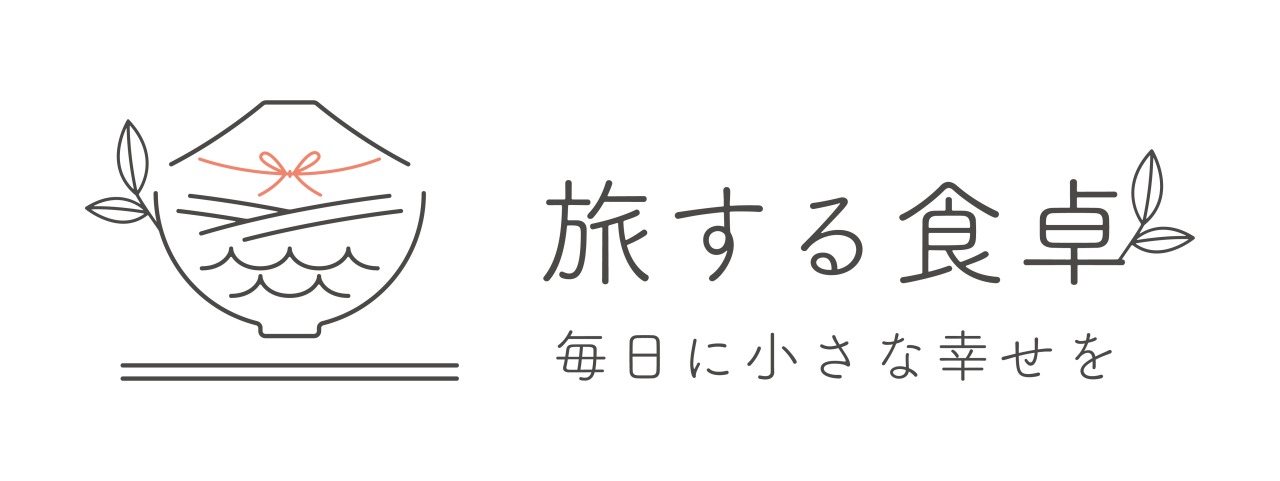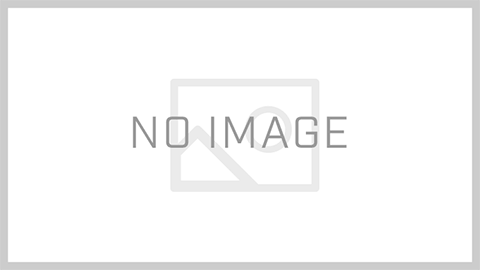おうちで旅気分
季節限定の味も一度に届いた夢のセット「やみつきしみかりせん」全7種を食べ比べ
2020年11月10日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
赤福だけじゃない!伊勢神宮のお土産にしたい餅菓子6選
2019年12月17日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
大津名物「三井寺力餅(みいでらちからもち)」は早いうちにめしあがれ!
2019年5月14日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分
カバヤ「フィンガーチョコ」に再会!金銀の包み紙が懐かしい
2018年8月18日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分
浜松市杏林堂限定!トリイのウスターソースをつかった本当においしいおせんべい
2018年3月23日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分
知ってた?関東と関西で雛祭りの「ひなあられ」はこんなに違う
2018年3月1日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
人の温かみと優しさを感じた「にいがた人形横町」
2018年1月4日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
新潟の上古町商店街、通称「カミフル」で見つけたステキなものたち
2017年12月26日 旅する食卓編集部 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip