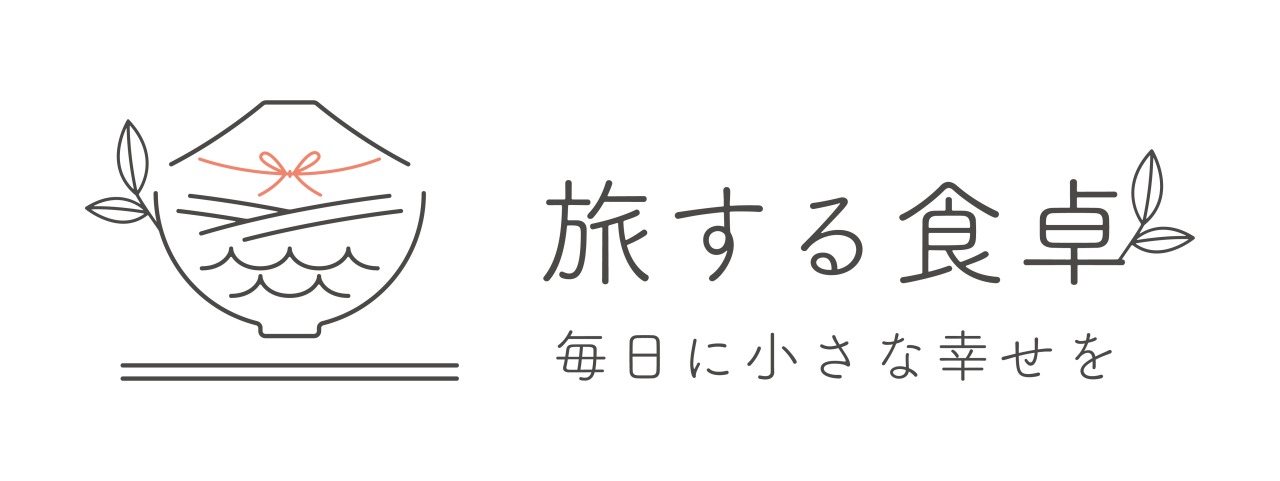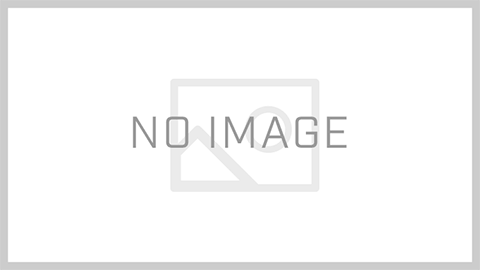季節イベントと食
【3月1日はデコポンの日】 デコポンと不知火は何が違う?美味しい食べ方は?
2024年2月28日 蒼井 翠 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おうちで旅気分
話題の白イチゴ「淡雪」から定番の「あまおう」まで7種のイチゴを食べ比べ!本当に美味しいのはどれ?
2020年2月21日 旅する食卓編集部 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip