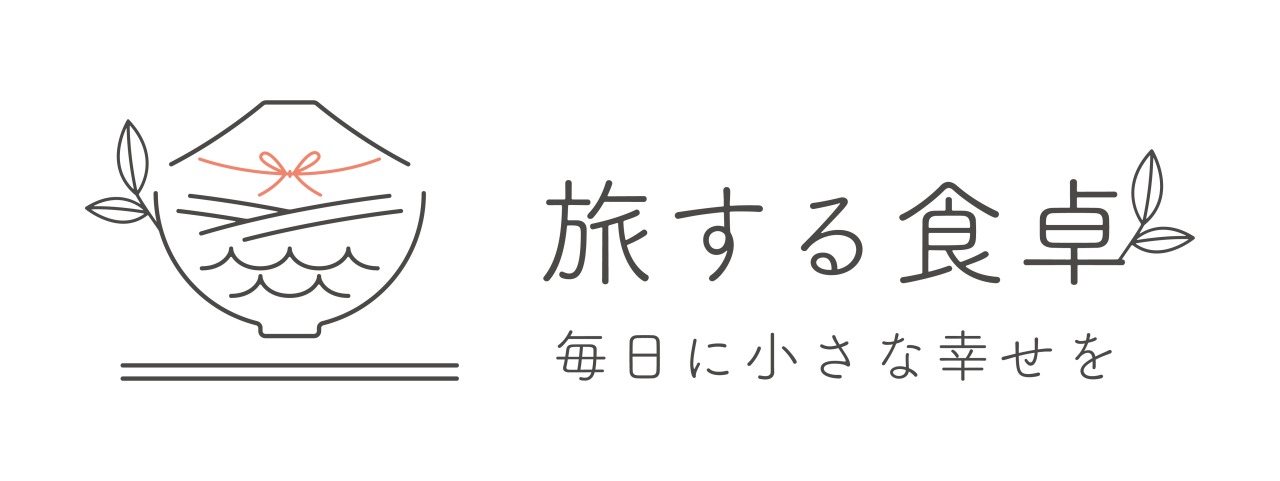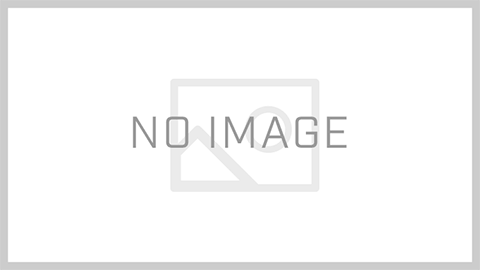おいしいもの巡り
シンプルイズベスト 京都人のソウルフード「志津屋」の「カルネ」
2024年9月17日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
【京都の定番土産】満月「阿闍梨餅」のできたてはどんなお味?
2024年3月11日 ひがのあや https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
京都の酒どころ【伏見】の酒蔵開きで日本酒三昧を楽しもう
2020年10月10日 くろかわ まさよ https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
京都土産に原了郭の【黒七味】! 食欲をそそる深い香り
2020年4月24日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

見学・体験レポート
【京都駅チカお土産スポット5】 定番のお土産からおしゃれなおもたせまでそろう「京都駅前地下街 ポルタ 東エリア」
2019年12月3日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
【京都駅チカお土産スポット4】 少しずついろいろ楽しめる「おみやげ小路 京小町 」
2019年12月1日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
たった3ヶ月だけの秋のお楽しみ「京都 くりや」の栗おはぎ
2019年10月25日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip

おいしいもの巡り
【京都駅チカお土産スポット3】 京都をギュッと凝縮!KYOTO TOWER SANDO(京都タワー サンド)
2019年10月24日 阿東いつ子 https://table-trip.com/wp-content/uploads/2024/09/旅する食卓_logo_yoko_color.png 旅する食卓 – table trip